ここ数ヶ月はめっきり哲学に関する本を読むことがなかった。というかここ数年は哲学に対して興味を失っていたので別に読みたいとも思わなかった。
学生時代は授業に出ても後ろの方で永井均の本ばかり読んでいたというのに、どうしてだろうと考えてみると答えはとても簡単で、「哲学書を読んだってお金にならないから」だと思う。学生時代は途中までは自分でお金を稼ぐ必要がなかったから現実には何の役にも立たない本ばかり読んで入られたけど、今はそうではなくなった。
しかし、より自分のスキルになり、即効力のあるような本ばかり読んでいるのは、それはそれで面白いのだけれど、やっぱりたまには全く役に立たない、でも何よりも興味深い問題について考えてみたくなってしまうのはもはや性分なのかも知れない。
というわけで久しぶりに哲学に関する本を読んだ。多分5年くらい前から読みたいと思っていたけれど、躊躇してしまっていた本だ。
「哲学の誤読 ―入試現代文で哲学する!」入不二基義著
タイトルのようにこの本では大学入試で実際に使われた現代文の文章を哲学的観点から徹底的に読み解く。4つの文章があるが全て現代の哲学者によって書かれた哲学に関する文章である。
しかし、著者で自身も哲学者である入不二基義氏によれば、これらの文章は「誤読」されているという。誰にか。それはこれらの入試問題を過去問として載せ出版している大手予備校や、出版社の解説者であるという。
受験生たちは赤本や青本の過去問を解き、解説を読むのだから、この解説が誤読であれば、受験生たちも誤読せざるをえない。受験生にとっては赤本、青本の解説はほとんど絶対的であり、解説に疑問を覚えることはまずないからである。
しかし、これは由々しき事態ではないのか。本来はもっと別の読み方、考え方があるにも関わらずに大学入試という狭いゲームの中での解釈で理解されてしまうのは許されざることである。しかも文章は前後を切り取られ、その文章が一部であった本全体の趣旨も捉えることが出来ずに。
特に哲学の文章を「人生論的」に誤読することが多い。これはもしかしたらまだ若い受験生を相手にしているから無意識的にこういう解釈をしてしまうということもあるかも知れない。しかし、哲学の文章は人生論とは一線を画する。
そこで著者の入不二氏はこれらの文章を徹底的に読み解き、哲学の文章の正しい読み方を解説する。いや、単に「これはこう意味だ」と解説しているのではない。だから解説するというよりは「実際に哲学をしているところを見せる」と言った方が適切である。
1つの文章に対して平均して60~70ページも割いていることからも、それがよく分かる。ただ単に答えを提示するだけではなく、実際に頭で考えるプロセスも全て文字にしてしまっているので、これだけ長いのだ。1つの文章をこれだけ長く(ねちっこく)解説した解説文は他に無いだろう。しかし、その分明快である。
そしてこれを読むのに哲学思想の基礎知識は必要無い。哲学することに知識は不要なのだ、ということも本の全体で証明している。必要なのは文章を読み解く意思と、論理的思考と、抽象的な概念を理解する力(想像力)くらいだ。寧ろ余計な知識は純粋な論理的思考を妨げてしまうかも知れない。
4人の哲学者
このこの文章を書いた4人の哲学者(野矢茂樹、永井均、中島義道、大森荘蔵)は哲学を齧ったことのある人なら誰もが知っているような一流の哲学者である。
大森荘蔵氏はもう他界されているが、他の3人の哲学者と著者の入不二氏は現在も第一線で活躍されている方々である。しかも生前の大森との交流もあったようであり、なんとも感慨深い。
この4人も一般人向けの哲学書を多く書いているが、中でも僕がおすすめするのをいくつか挙げておきます。全て哲学が持つ難解なイメージが皆無の個性的な本ばかりです。
4つの入試現代文
ここでは4つの入試現代文の大まかな趣旨とそれについて僕自身がどう考えたのかをちょろっと書く。著者自身の解説はあまりに長く緻密なのでここには書ききれない。
興味のある人は是非買って下さい。
野矢茂樹「他者という謎」(哲学・航海日誌)(北海道大学入試)
他人の痛みを理解出来るか
この文章のテーマは「他人の痛みを理解出来るか」ということである。
我々は自分の「痛み」は当然理解出来る。包丁で指を切ってしまえば当然痛いし、タンスの角に足の小指をぶつけたら泣き叫ぶことのしばしばである。
しかし「他人の痛み」についてはどこまで理解しているだろうか。我々は「他人の痛み」をどこまで理解出来るだろうか。ここが野矢の疑問の出発点である。
ざっくりいうと文章はこんな風に展開していく。
「他人の痛み」は自分に理解出来るのか?
↓
全ては理解出来ないとしても日常的な感覚として「少しは分かる」はずだ(顔の歪み、出血等から)
↓
しかし「顔の歪み」や「出血」は外面的な特徴でしかない。内面的な「痛み」はどこにあるのか?
↓
もしかしたら他人の「心の中」にあるのかも知れない。
↓
でも、仮にあったとしてもそれは本当に「私の痛み」と同じ「痛み」なのか?
↓
仮に私が「他人の痛み」を感じたって、それは詰まる所「私の痛み」ではないか?
なぜなら「痛み」を感じているのは「私」だから。
ざっくりこんな風に展開していく。問いを立て、それに答える。しかし満足がいかないので更に問いを立てる。更に問いに答える。その繰り返しであり終わりはない。これこそまさに「哲学をする」ということだ。
この文章が書いてある本のタイトルは「他者という謎」だから、おそらく「痛み(感覚)」を出発点にして、「他者は本当に存在するのか?」「この世界には自分しか存在しないのではないか?」という更に大きな問いへと続いていくだろうと予想出来る。「痛み」という小さな問題を手がかりにして独我論にまで昇華する。
「痛み」の所在(場所)について
本文の中では「他者の痛み」の場所についての言及があったが、自分でも他者でもいいから、「そもそもどこが痛いのか」というのはまた別の興味深い問題である。
例えば指を切ったとする。当然痛いし泣き叫ぶだろう。しかし一体いたのはどこなのか?まず真っ先に思いつくのはケガをした指先である。血がドバドバ出てるし、ジンジンする。
しかしちょっとませた奴は「痛みは脳が感じているんだ」と言うだろう。なるほど確かに脳(そして神経)がなければ我々は痛みだけでなく感覚一般を感じることが出来なくなる。
しかしそれでも頭蓋骨の中にある「脳みそ」が痛いと言うわけではないだろう。別に頭痛がするわけではない。痛いのはやっぱり指先である。
とは言っても指先「が」痛みを感じているわけではない。あくまで(我々が)指先「で(を介して)」痛みを感じているのである。指先は痛みの原因ではあっても痛みそのものではない。
じゃあやっぱり脳かと言うとさっきの話に逆戻りしてしまう。一体痛みはどこにあるのか?そもそも「痛み」なんてあるのか?
これ以上は長くなってしまうのでここでやめよう。でも問題は「痛みの場所」という時の「場所」という言葉の使われ方にあるような気がする。
永井均「解釈学・系譜学・考古学」(転校生とブラックジャック)(東京大学入試)
永井均は僕が学生時代に病的に愛読した哲学者の一人である。主に独我論、倫理道徳に関する著書が多く、専門書だけではなく一般人向けに易しく書かれた著書も多数ある。中でも「マンガで哲学する」は数ある哲学書の中でもユニークな本で漫画好きは必読と言える。
東大の入試に使われた「解釈学・系譜学・考古学」は「チルチルミチルの青い鳥」のストーリーに対してこの3つの解釈が成り立つことを示しつつ我々が考える常識的な「過去のあり方」とは別の「過去のあり方」について論じている。
こう書いたってほとんどの人はチンプンカンプンに違いない。僕自身も著者の解説が無ければ理解出来ない点が多かった。さすが東大。これを制限時間内に解けというのは無理ゲーである。
しかし「難解さ」は「解釈学・系譜学・考古学」と言った用語にあるのではなく、永井の洗練された文章と思考の深さにこそあると思う。別に用語を知らなかったとしても解けないことはない。
チルチルミチルの青い鳥
僕はチルチルミチルのお話を忘れていたのだがこんな話らしい。
2人兄妹のチルチルとミチルが、夢の中で過去や未来の国に幸福の象徴である青い鳥を探しに行くが、結局のところそれは自分達に最も手近なところにある、鳥籠の中にあったという物語。(wikpedia)
解釈学的解釈
これを解釈学的に解釈すると「青い鳥はチルチルミチル が旅に出る前から、元々青かった。そして二人は鳥が青いと気付く前から幸福だったことを悟る」ということになる。
つまり「これまでもずっと鳥が青いということは、二人はこれまでもずっと幸福だった(なぜなら青い鳥がいたから)」という風に解釈することが出来る。これが解釈学的解釈である。
青い鳥はチルチルミチルが気付く前からずっと青かった。(本人たちの視点)
この考え方は常識的な過去観だから理解するのにそれほど難しくはない。問題は次からだ。
系譜学的解釈
系譜学的視点を入れると少し違った様相を見せる。系譜学的な観点の元ではチルチルミチルの話は「鳥はある時点で青かったことになった」という複合的な視点が導入される。
つまり「本当は青くはなかった」のだけれど「ある時点で「(元々)青かった」ということにされた」という解釈である。要するにチルチルミチルの記憶が根本的に間違っている、という解釈である。
もちろん単なる記憶違いなどではなく、これは超越的視点から「間違っている」と言えるのであって当の本人たちはそれが間違いであることをもはや疑うことは出来ない。
これはもはや「元々青くなかったけど途中で青くなった」というような素朴な時間軸では考えられず、「青かったか、青くなかったか」の2つに1つではない。
つまり系譜学的解釈とは読者(外部・神・超越的視点)の立場にある我々がチルチルミチルの話を解釈する視点なのである。
青い鳥はある時点で「元々青かった」ということになった(我々読者の視点)
考古学的解釈
しかし「系譜学的解釈」すらも跳ね除けるような過去のあり方は存在する。それが考古学的解釈である。考古学的解釈は、解釈学的解釈のように「鳥は元々青かった」、系譜学的解釈のように「ある時点で「青かった」ということにされた」というような解釈は出来ない。
もはや過去は現在(二人が鳥が青いことに気付き幸福だったことを悟る)になんの影響も与えることは出来ない。
考古学的過去とは、定義上、絶対に思い出すことの出来ないような過去である。過去は実在してはいたが、我々の認識のはるか遠いところにある。それはもはや「歴史に埋もれた過去」とも形容することの出来ない、「そうであった」とも「そうでなかった」とも言えないような過去である。
鳥は青かったとも、青くなかったとも言えない。端的にそんな観点は存在しなかった(実在論的視点)
3つの過去のあり方
ここでは3つの過去のあり方について考えられており、解釈学→系譜学→考古学に至ると共に過去の過去性が強固になっている。
- 解釈学的過去 チルチルミチルたちによって解釈される過去(弱)
- 系譜学的過去 我々読者(超越的視点)から解釈される過去(中)
- 考古学的過去 もはや誰にも解釈することが出来ない(現在との関係の中で語ることの出来ない)ような過去(強)
しかし疑問なのは「そもそも考古学的過去なんていうものは存在するのか」ということだ。考古学的によるとチルチルミチルの鳥はその時点では「青かったわけでもなく、青くなかったわけでもなかった」ということだが、そんなことは現実においてはあり得ない。
論理的に鳥は青かったか、青くなかったかのどちらかであるはずである。
しかし「鳥は青かったか、そうでなかったか」という視点は解釈学的解釈に逆戻りしてしまう。つまり考古学的視点なんていうものが存在するのは論理的に不可能ではないか。そんなものがあったとしても、もはや我々は「そんなものがあった」と語ることすら許されないのではないか。
ここでもやはり言葉の問題(文法・論理形式)が鍵になっていると思う。
中島義道「幻想としての未来」(時間論)(早稲田大学入試)
中島義道について
中島は他の3人と比べてかなり異色な(個性的な)哲学者と言える。
元々東大の法学部に進むはずだったが「自分が明日死ぬとしたら、いま何を学びたいか」と考えて哲学科に入り卒業。大学院に進むが陰鬱な雰囲気に耐えかねて途中で退学。
しかしその後法学部に学士入学し卒業するが、法科大学院にはいかずに再び哲学科の大学院に進み修士号を取得する。
それから30代で私費でウィーン大学に行き哲学博士号を取得する。その後は東大で助手をしたり、電気通信大学の教授を務めたりしている。
こう書くととんでもないエリートのように思えるが、実際は物理が理解出来なくて留年したり、同僚からいじめを受けたりととても人間的なエピソードがたくさんある。
この人の著書も「私の嫌いな10の言葉」や「不幸論」や「どうせ死んでしまう…… 私は哲学病。」と言ったネガティブなタイトルばかりで個人的には一番親近感が湧く哲学者である。
中島義道の「時間論」
早稲田の入試に使われた文章のテーマは「未来なんて<ない>」であり、これは中島の一貫した主張である。中島によれば未来は「現在の心の状態」に過ぎない。
例えば、「明日また会社で働くだろう」と予想したとする。きっと99パーセントそうなるだろう。しかし、中島によればこの予想はあくまで予想であり、「未来そのもの」ではないという。予想は外れることがあるのだ。
じゃあ例えば物理法則なんかはどうだろうか。例えば「明日も水は摂氏100度で水蒸気になる」と言った予想は100パーセントそうなるはずではないか。
中島はこの問いに対しても異を唱える。確かに物理法則は会社に行くかどうかよりも確からしく見えるが、これも言ってしまえば「これまでそうだったから」という単純な理由を前提としており、本当はそんな保証はないと言う。
昨日までちゃんと飛んでいた飛行機が明日も同じように飛ぶ理由は、実際のところ「これまでもそうだったから」という理由以外に見つからない。物理法則が明日も今日と全く同じように作用するかどうかは、誰にも分からないのだ。つまり未来は「現在の心の状態(想像)」に過ぎない。
時間軸のスライド・過去→現在(未来)から現在→未来は導き出せない
どうしてこんなことが起こってしまったのか。それは過去から現在へと至る時間軸を未来にまで延長してしまったことが原因だと考えられる。
過去における未来は確かに存在する。例えば一昨日から見た昨日は未来だけれど、それは確かに存在していた。しかしその未来(昨日)が存在していたと確実に言える理由は、今日の時点では一昨日には未来であった昨日は、もう既に過去のことだからである。こういった「過去における未来」という時間のあり方は誰も了解しているし、「現在の心の状態」ということも出来ない。
しかし、この過去から現在に至る時間軸をむやみに未来まで延ばすことは出来ない。現在からみた未来はまだ「過去における未来」ではないから同じ時間のあり方をしているかどうかは誰にも分らない。
達成動詞と仕事動詞
未来は誰にも分からないが、過去についてはもうはっきりしている。記憶違いがあったとしても、記憶違いではない「本当の過去」は存在する。何故なら記憶違いする為には本当の過去が必要だからだ。
中島はここでG・ライルが用いた「達成動詞」と「仕事動詞」という文法上の分類を例に挙げて、過去の実在性・未来の非実在性について説明する。
達成動詞とは動詞の意味の中に何かを達成したことが示されている動詞であり、arrive(着く)やfind(見つける)のことである。この種類の動詞はいわば現実の対象に届いている動詞である。「見つけた」のならもう既に何かを見つけているのでなければならない。
もう1つの仕事動詞とは仕事の遂行自体を表す動詞でありwork(働く)やhunt(狩りをする)などである。こちらの動詞は「達成」が含意されたおらず、対象には届いていない。そもそも対象に届くかどうかは問題になっていない。
問題は「予想する」や「予測する」といった未来に対して何らかのアプローチを取る動詞がどちらに分類させるか、ということだ。
これらの動詞は一見達成動詞のようにも見えるがそうではない。何故なら未来の出来事を「予測した」としてもそれはあくまで「予測」であり、実際にそうなる(達成される)保証はどこにもない。「予測したのに外れた」ことはいくらだってありえる。
しかし、過去に対して「想起する」「思い出す」と言ったアプローチを取った場合には「想起したのに想起が外れる」ことはありえないし、「思い出したけど思い出したことが外れる」ことはあり得ない。何故ならこれらは達成動詞であり対象に届いているからである。思い出した内容が間違っていようとも対象に届いていないことはあり得ない。
となると未来について何かを語る時には達成動詞を使うことを出来ないから、未来は我々の手の届く対象というあり方をしていない。つまり未来は現在の我々の想像に過ぎない、というのが中島の主張である。
「心の中で想像する未来」と「絶対に想像出来ない本当の<未来>
入試現代文の中で論じられているのは「未来なんて現在の心の状態に過ぎない」ということだけであり、設問に答えるにはこれだけ理解していれば事足りる。しかし入不二氏は更に深読みする。
上にもあるように未来について何かをいう為には達成動詞を使うことが出来ず、その意味では未来は我々の手の届く対象というあり方をしていない。だから未来について何かを語る時は全て現在の我々の想像でしかない、という結論に至るのだが、我々の手の届く対象というあり方をしていなくても、やはりそれは我々の手の届かない対象というあり方で存在するのではないか。
寧ろ<本当の未来>は必然的にそういうあり方で存在しているのではないか。
イメージで言えばこうである。我々の手の届く範囲というものがあるとして、そこに線を引く。例えば、白い紙の上に一本縦に線を引いてみる。左側が我々の手の届く範囲だとすると、右側が手の届かない範囲である。
つまり手の届く範囲(対象)という風に限定してしまうとどうやっても「手の届かない範囲」も出てきてしまう。
この絶対に我々の手が届かないが故に存在するような<本当の未来>、をチルチルミチルの話の「考古学的過去」と比べてみると非常に興味深い。もし中島と永井の議論がどちらも正しいとなれば、我々にあるのはこの「現在」だけということになる。
大森荘蔵「「後の祭り」を祈る」(時は流れず)(名古屋大学入試)



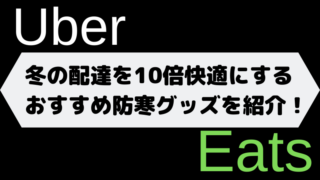
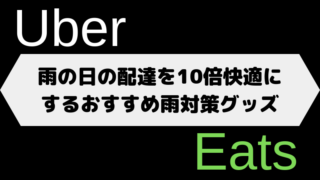
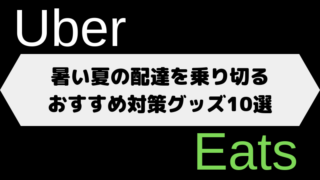
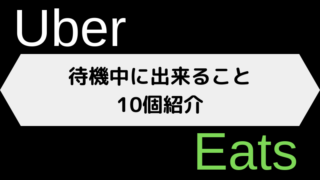
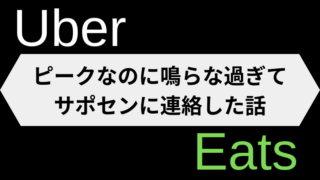
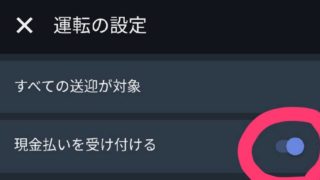

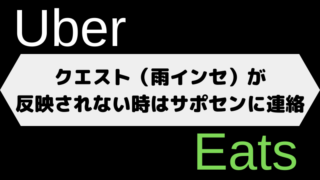
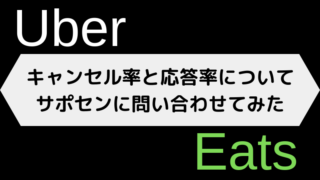
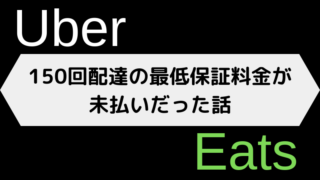
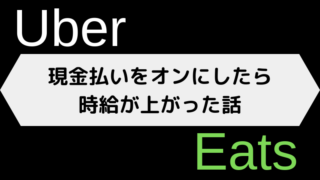


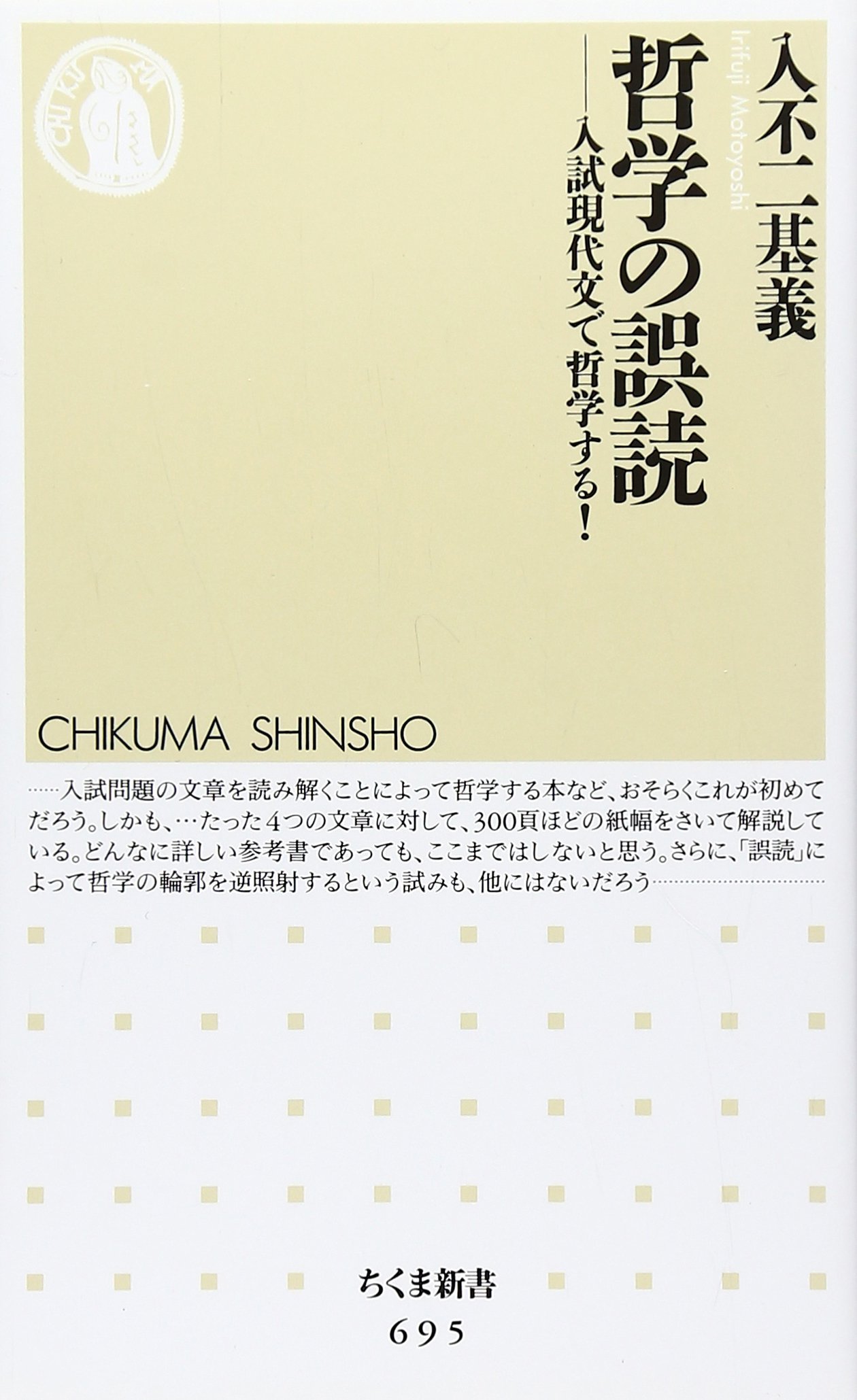





コメント